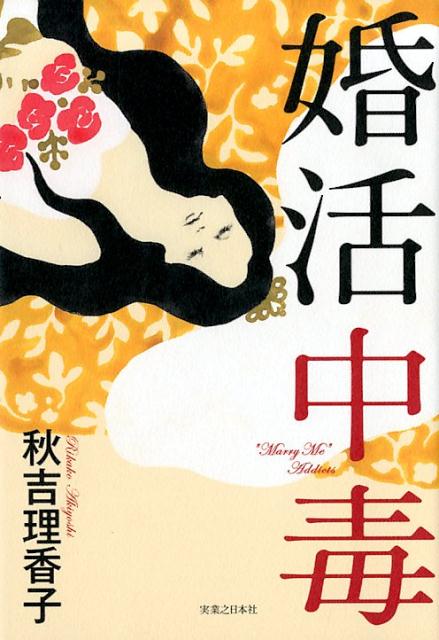こんにちは!小町です。
前回に引き続き、多崎礼さんの「レーエンデ国物語」シリーズです。
今回は3作目ですが、前作のラストがつらくて、次こそはなんとか革命の芽が摘まれないで欲しいと願うばかりです。
\前回の記事はこちら/
\1作目の記事はこちら/
あらすじ
戦争のない時代は、聖イジョルニ帝国とレーエンデに芸術と産業の発展をもたらした。聖都のルミニエル座の俳優アーロウと双子の兄で劇作家のリーアンは、ある演出家からの執筆依頼に、レーエンデの英雄とその隠された物語を題材に選ぶ。英雄の足跡をたどる旅に出た二人が見たものは――
芸術の力で
初代法皇帝エドアルド・ダンブロシオには嫌な感情しかありませんが、良かったこととしては、レーエンデへの支配に注力するためとは言え、長く続いた戦争を終わらせたことでしょうか。
平和な時代には、芸術や産業が花開くものです。
いつのまにかレーエンデの地にも鉄道が走り、各地に劇場ができていたりと、随分雰囲気が変わりました。
一見、平和で華やかに見える世界ですが、変わらず虐げられるレーエンデ人たち。終わらない重税に差別、そんな状況を受け入れ、あきらめてしまった人々の光景は、前作よりも状況が悪くなっているように思えます。
そんな中、レーエンデの劇場(実際は娼館のことですね)で生まれた双子の兄弟。
弟のアーロウは、生まれた劇場で俳優として、変わり者の兄リーアンは劇作家として本を売って生活し、反発しながらもお互いを想っている関係なのがわかります。
二人はあることをきっかけに歴史から消されてしまったレーエンデの英雄について書くことを決め、その生涯を追いかけることになりました。
その英雄は言わずもがな、前作の主人公テッサです。
前作のつらい展開を思い出し、胸が苦しくなりましたが、
あの壮絶な出来事の詳細どころか後世に名前も残されなかったことが衝撃でした。
兄のリーアンは彼女の物語を世に出すことで、レーエンデ人だけではなく、イジョルニ人の心も動かしたいと考えていました。レーエンデが本当に自由を得るためにはイジョルニ人をも動かすことが必要だと、芸術にはそれを成し遂げる力があると、信じていたのです。
武力ではなく芸術の力で。
革命の火を灯そうとした生涯もまた、テッサ達とは違った形で、儚く。
双子の話といえば、入れ替わりがつきものでございます。
リーアンとアーロウは互いに思いやりながらもそれを伝えることが苦手で、こんな場面で双子の仕掛けを効果的に使うのはつらい!と思いましたが、双子とはなるべくして、それぞれの役割のために生まれてきたのかもしれませんね。
3作目は今までのような戦いのシーンはほとんどなく、双子の苦悩や葛藤、愛情など心理的な部分が多く描かれます。
また構成としては、各章の合間に「月と太陽」の上演がはさみこまれており、
戯曲が完成し世に出ていることを私たち読者は知りながら、それまでの双子の物語を追いかけていくことになります。
革命の火は灯ったか
イジョルニ人の心も動かす。
その試みは、良い方向になる予感がします。
魅力的な登場人物である、イジョルニ人のミラベルや、前作登場した司祭長リウッツィ家など、真心のある人たちの存在が希望の兆しだと思います。
前作でテッサが助けた少年の子孫や、娼館の人たち、パン屋の店主などの登場で地続きの物語であることを気づかせてくれますし、なにより名もない一人ひとりが繋いできた小さなことが大きな流れになっていく感じが、無駄なことは無いのだと思わせてくれました。少し報われた気持ちです。
しかし2作目の時、レーエンデの人々が団結できなかったことで綻んでしまったことを思い出します。まだ、何かが足りないのでしょうか。
見せかけでも平和の中、我慢さえすれば、生きていける。そんな状況に声を上げることはつもない勇気が必要で、まして人々の心に火を灯し、団結するということは簡単ではありません。
個人的には、今の日本も言えることが多いなと思います。
我慢すれば、自分はどうにか生きていけているし、現状でもいいやとあきらめてしまっている奴隷根性が変革を妨げていると。
ここからまだ革命を起こすに至るには、まだ少し時間がかかるかもしれません。
テッサの物語が上演されたことの影響はここではまだ明らかには書かれませんでした。
双子の人生をかけた行動が、未来の大きな一歩になることを次回作にて期待しております。